【ムーミン】ムーミン一家の帰りを待つ人たちの物語。シリーズ8作目。【ムーミン谷の十一月】【小学校高学年以上】
ムーミンたちが海の灯台に移り住んでいる頃、スナフキンやフィリフヨンカ、ヘムレン、スクルットおじさん、ミムラ、ホムサたちは、ムーミン屋敷に集まってきました。ムーミンたちの帰りを待ちながら、奇妙な共同生活をはじめます……
この本のイメージ ムーミン一家は登場しない☆☆☆☆☆ 自分とは何か☆☆☆☆☆ かなり哲学的☆☆☆☆☆
ムーミン谷の十一月 ムーミン全集 8 トーベ・ヤンソン/作 鈴木徹郎/訳 講談社
<トーベ・ヤンソン>
画家・作家。1914年8月9日フィンランドの首都ヘルシンキに生まれる。父は彫刻家、母は画家という芸術一家に育ち、15歳のころには、挿絵画家としての仕事をはじめた。ストックホルムとパリで絵を学び、1948年に出版した「たのしいムーミン一家」が世界中で評判に。1966年国際アンデルセン大賞、1984年フィンランド国民文学賞受賞。おもな作品に「ムーミン童話」シリーズ(全9巻)のほか、「少女ソフィアの夏」「彫刻家の娘」などがある。
<鈴木徹郎>
北欧文学者・翻訳家。1922年長野県生まれ。スウェーデン語、デンマーク語に精通し、北欧の名作を数多く日本に紹介した。のち、デンマークのコペンハーゲン大学大学院に留学し、アンデルセン文学の研究を進めた。国際アンデルセン学会会員となり、日本アンデルセン教会事務局長を務めた。著書に「ハンス・クリスチャンセン・アンデルセンーその虚像と実像ー」(日本児童文学学会奨励賞)、訳書に「アンデルセン小説・紀行文学全集」(全10巻)などがある。1990年逝去。

ムーミン全集第8巻「ムーミン谷の十一月」。原題は Senti November.本国初版は1970年。日本語初版は1980年、新装版が2011年、そして、ムーミン全集としての初版は2020年です。
児童文学の形で始まったムーミンですが、「ムーミンパパ海へいく」あたりから、哲学的な展開を見せはじめ、この「ムーミン谷の十一月」では、かなり純文学的な、内省的なお話になっています。
ムーミン一家がムーミンパパの思いつきで一家揃って灯台に引っ越したとは知らず、フィリフヨンカ、スナフキン、へムレンさん、スクルットおじさん、ホムサ、ミムラ姉さんがそれぞれの事情でムーミン屋敷に集まってきます。
スナフキンは、見失ってしまった音楽の1小節を探しに、フィリフヨンカは掃除をしていたときの事故のトラウマを癒しに、スクルットおじさんは自分を尊重してくれる場所を探しに、へムレンさんは新しい何かを探しに、ホムサはあたたかい家を探しに、と言ったぐあいにです。
そうそう、ミムラ姉さんは、何も探していません。この人は、ミイとおなじで心にまったく不足はなく、マイペースなのでした。
心にどこか欠けたところのあるメンバーの中で、マイペースなミムラ姉さんがちょうどいい潤滑剤と接着剤になってくれます。さすがはミムラ姉さん。
「ムーミンパパ海へいく」は、ムーミンパパが見失った自分を取り戻すために、家族全員引き連れて灯台に引っ越すお話でした。(かなり迷惑……)
物語の中でムーミンママでさえ、一時はうつ病のような症状を発してしまいます。
しかし、最後は消えてた灯台に灯がともり、それがムーミンパパの自己回復の象徴となっています。(こけだけ書くとわけがわからないと思いますので、ぜひお読みくださいね。とはいえ、かなり哲学的な内容です)
「ムーミンパパ海へいく」と「ムーミン谷の十一月」は、どちらも人生の中年期に自分の人生を振り返り、様々な疑問や悩みを抱く、所謂「中年の危機」がテーマになっているので、子どもが読むとぴんとこないかもしれません。しかし、読みやすい文体で書かれているので、子どもの頃に一度読んでおくと、大人になったときに「ああ、あれはこういう意味だったのか」と腑に落ちると思います。
また、これを読むと大人は何でもわかっているわけではなく、大人には大人なりの悩みがあるのだと思うかもしれません。
「ムーミンパパ海へいく」では、ちびのミィだけは、ムーミン一家のそれぞれの心の葛藤などなんのその、まったくのマイペースで快適に灯台での暮らしを満喫していました。
それと同様に、誰もいないムーミン屋敷での奇妙な共同生活においても、ミムラ姉さんだけはまったくマイペースで、楽しく暮らしています。
それに、ミムラ姉さんは、なかなかコミュ力が高くて、うまく周囲をおだてたり、楽しい気分にさせたりして、ぎすぎすした雰囲気を上手に丸く収めてしまうのです。
ムーミンママと違うのは、ママのように全部譲ってしまうのではなく、ミムラ姉さん自身もちゃっかり得をするところ。
でも、このマイペースなミムラ姉さんのおかげで、フィリフヨンカは少しだけ積極的になれます。
わたし自身、子どものころ「ムーミンパパ海へいく」を読んだときはムーミンパパがあまりにも勝手すぎて憤慨していましたし、「ムーミン谷の十一月」はムーミンとスナフキンがちゃんと再会するところまで書いてほしい、と思っていましたから、この2冊は子どもが読んだときに満足感が得られるかどうかは、ちょっとわかりません。
けれども、純文学的な魅力があるし、子どもでもそういう小説が好きな子はいるので、深く読み込む子もいるかもしれません。
ただし、人生の挫折を経験し、自分のいままでとこれからに迷いを感じたことがある大人のほうが、たくさんのことを感じ取れると思います。親子で感想を語り合っても、興味深い体験ができるかも。
文章自体は読みやすく、難しい漢字には振り仮名が振ってあるので、このブログでは「小学校高学年以上」とします。しかし、内容はたいへん深く、哲学的です。
ムーミンシリーズは、ここで綺麗に完結していますが、初期に執筆された「小さなトロールと大きな洪水」がムーミン全集の最終巻として刊行されてます。近いうちに、この本も読む予定です。
全部読むと、長い旅を終えたような気分になるムーミンシリーズ。長い冬にあたたかい部屋で読むのにぴったりです。熱いコーヒーを用意して、じっくり読んでみませんか。
一度読んだことがある人も、もう一度読むと、かならず新しい発見があります。それが、ムーミンの魅力なのです。
繊細な方へ(HSPのためのブックガイド)
幻想的で哲学的なお話です。HSPやHSCのほうが多くのメッセージを受け取れるでしょう。
ムーミンシリーズは、「正解はこれだ」と解釈を押し付けてくるお話ではないので、自分なりの考察を楽しむ喜びがあります。
子どもが読んでも、大人が読んでも、ちがった世界が見える名作です。
たっぷりと時間をとって、しずかな部屋で、または公園のベンチなどで読むのにおすすめです。

![ムーミン全集[新版]8 ムーミン谷の十一月 (ムーミン全集 新版 8)](https://m.media-amazon.com/images/I/510sfp4YdoL._SL500_.jpg)
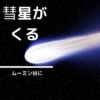

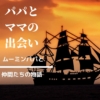


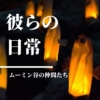









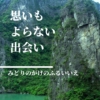
最近のコメント