【バレエシューズ】血のつながらない三姉妹の物語。色あせない児童文学の名作です。【小学校高学年以上】
1930年のロンドン。身寄りのない三人の赤ちゃんがある学者に引き取られます。成長した三姉妹は「フォシル」と名乗り、歴史に名を残そうと誓い合うのでした……世界中で愛される色あせない名作。
この本のイメージ 女の子の自己実現☆☆☆☆☆ 成長物語☆☆☆☆☆ 家族愛☆☆☆☆☆
バレエシューズ ノエル・ストレトフィールド/作 朽木洋/訳 金子恵/画 福音館
<ノエル・ストレトフィールド>
1895年、英国のサセックス州に生まれる。英国王立演劇学院を卒業後、女優として活動。1931年に児童書の創作を始め、1936年刊行の「Ballet Shoes」にて一躍人気作家となる。1939年に「Circus is coming」(アメリカ版タイトル「Circus Shoes」)にてカーネギー賞を受賞。1986年没。
<朽木洋>
広島市生まれ。被爆二世。上智大学大学院博士前期課程修了。Postgraduate diploma course of Trinity College, Dublin 修了。著書に「かはたれ」(児童文芸新人賞、日本児童文学者協会新人賞ほか受賞/福音館書店)、「風の靴」(産経児童出版文化賞大賞/講談社)、「光のうつしえ」(小学館児童出版文化賞、福田清人賞/講談社)、「彼岸花はきつねのかんざし」(日本児童文芸家協会賞/学習研究社)、「あひるの手紙」(日本児童文学者協会賞/佼成出版社)、「オン・ザ・ライン」(全国青少年読書感想文コンクール指定図書/小学館)、「たそかれ」(福音館書店)、「引き出しの中の家」(ポプラ社)、「八月の光 失われた声に耳をすませて」(小学館) など多数。鎌倉市在住。
<金子恵>
書籍の挿絵、装幀画を多く手がける。「引き出しの中の家」(ポプラ社)、「たまごを持つように」「鉄のしぶきがはねる」「鷹のように帆をあげて」(以上、講談社)、「夜をゆく飛行機」(中央公論新社)、「神去りなあなあ日常」「神去りなあなあ夜話」(以上、徳間書店)、「ごきげんな裏階段」(新潮社)など多数。

非常に有名な児童文学の名作ですが、わたしは初読です。
大人になってから、友人に熱烈に魅力を語られた記憶があるのを最近になって思い出し、「これは読まなくては」と選びました。
原題はBallet Shoes.イギリスでの初版は1936年。日本語版は村岡花子訳が1957年、中村妙子訳1979年、久米穣訳1980年、中村妙子新訳2018年(すみません、敬称略)、そしてこの新訳が2019年です。
現在最も入手しやすいのは、この福音館出版 朽木洋先生訳版ですが、中村妙子先生の新訳版もマーケットプレイスなどでは流通しています。
お話は……
化石収集家のマシュー・ブラウン教授は、旅に出ては化石やなにやら海外の不思議な発見物を家に持ち帰るのが常でした。
彼の甥の娘、シルヴィアは、両親を失ったあとブラウン教授に引き取られ、彼の屋敷をきりもりしていましたが、おかしなみやげ物を持ち帰るブラウン教授の癖は、だんだんエスカレートし、ついに身寄りの無い赤ちゃんを連れてくるようになりました。
しかも三度の旅で三人。みんな女の子の赤ちゃんです。
最初の赤ちゃんは難破船から救助された美少女ポーリィン。次の赤ちゃんは病院で息をひきとろうとするロシア人から託されたペトローヴァ。3番めの赤ちゃんはバレエシューズとともに貧しい女性から託されたポゥジーです。
三人は自分たちの名字を「フォシル(化石)」と名乗り、この三人だけの特別な名字を歴史に残そうと誓い合うのでした。
やがて、三人は児童ダンス演劇アカデミーに通うようになり、舞台に立つことになるのですが……
……と、言うのがあらすじ。

三人を養子にしくれたマシュー・ブラウン教授(通称グレート・アンクル・マシュー。略してGUM(ガム)は、放浪癖があり、何年も家を留守にしては、冒険旅行で手に入れた発見物を家に置いてまた出かけてしまうという人でした。
三人の赤ちゃんを養子にしたあと、GUMは五年分の生活費を残して、行方知れずになってしまいます。
シルヴィアと乳母のナナはやりくりして生活していましたが、だんだんと苦しくなり、家に下宿人を置いて生活を支えようと決意。この下宿人の方々が、研究者やダンサーだったことから、三人は彼らから様々な教育を受け、やがて家計を支えるために児童ダンス演劇アカデミーに通うことになりました。
大人たちは彼女たちに才能があると思い、三姉妹は子役として舞台に立てるようになれば苦しい家計を支えられるようになると思ったからでした。
長女のポーリィンは輝くばかりの美少女、次女のペトローヴァは理系の才能がある女の子、三女のポゥジーはバレエの才能があります。
それぞれがそれぞれの力で、自分たちの「家」を守るために努力し、最終的にそれぞれの歩む道を見つけるお話です。
ポーリィンの小さな子どもなりの山あり谷あり失敗あり成長ありの物語がオーソドックスな展開だとすれば、ポゥジーの成長は突き抜けた天才の物語です。
幼いポゥジーは、バレエに対する情熱と才能ではちきれんばかりで時々奇異に見える行動をします。
そして、次女のペトローヴァは「女の子らしくない」数学や機械、車や飛行機が大好き。まだまだ封建的な価値観がある時代に「らしさ」についての悩みを抱えています。
わたしがこの時代の児童文学が好きなのは、物語が尻上がりに盛り上がってゆき、ラストのどんでん返しで今まで苦しかった状況が一気に大逆転する爽快感からかもしれません。「小公女」もそのパターンですが、やはりカタルシスがあります。
この「バレエシューズ」も、なかなか帰宅しないブラウン教授の留守を守りつつ、シルヴィアとナナと三姉妹は経済的に日々苦しい思いをしながらも、支えあい励ましあって、様々な困難を乗り越えてゆきます。
まだまだ女性が働くのは難しかった時代に、シルヴィアと乳母のナナがやりくりしながら子どもたちを支える姿にも、胸を打たれます。これは、シルヴィアとナナの成長物語でもあるのです。
屋敷で暮らす下宿人たちもいい人ばかり。知恵を絞って相手の自尊心を傷つけずにほどよい距離から助けてくれます。この絶妙な距離感と、要所要所で提案されるアイディアに脱帽。
経済的にはけっして豊かではないし、逆にGUMの不在が長いことで、ずるずると下降気味になってゆくなか、登場人物たちのあたたかな交流が心にしみるのです。
なにしろ、GUM屋敷で暮らす人々はシンプソン夫妻のふたり以外はそれぞれ全員他人なのですから。
血のつながりなど無くても、ここまで強固なつながりがあれば、これは立派な家族だし、下宿人の面々も親戚のようなもの。
これ、1936年の作品です。なんて新しい家族観なのでしょう。
ジェイクス先生から「先祖の名と何の関係も無く、自分たちだけの名字で名をあげられる幸せがある」と励まされ、孤児の三姉妹が歴史に名を残す決意をするこのお話の根底には、「血縁」や「家柄」に対する挑戦のようなものが感じられます。
血がつながっていなくても家族になれる、家柄が良くなくても成功することができる……
この物語が、三姉妹が家柄や血のつながりで悩むことになるだろう恋愛や結婚の適齢期になる前に潔く終わっているのもさわやかです。もちろん、三姉妹ならそれらの障害も乗り越えるのでしょうけれども、ここでスパンと終わっているほうが、彼女たちのひたむきな思いが伝わります。
それぞれの夢を追い、それぞれの人生を生きることになっても、何があってもいつまでも三人は姉妹なのです。たとえ、一滴も血がつながっていなくても。
これが1936年に出版されたとは思えない新しさ。
かなりのボリュームですが、ロンドンのクラシックな雰囲気を楽しみつつ、少女たちのあどけなくも力強い歩みに共感しながら、ぐいぐいとラストまで読めてしまいます。
難しい漢字には振り仮名が振ってありますが、全部ではないので小学校高学年から。けれど、これはむしろ大人のほうが楽しめるかもしれません。
窮屈な固定観念をしなやかに飛び越えてくれる児童文学です。
まだの方には今こそ、この瑞々しくさわやかな感性に触れてみてくださいね。
繊細な方へ(HSPのためのブックガイド)
ネガティブな要素はまったくありません。
波乱万丈のストーリーを楽しんでいるうちに、「家柄」「血のつながり」「家族」「姉妹」「女性の生き方」「女の子らしさ」などの固定観念を、いつの間にか軽やかに越えてゆくストーリーです。
これが80年以上前に書かれたと言うのが驚きです。
読後は、シルヴィアとペトローヴァみたいに温かいココアとビスケットでひと休みしましょう。






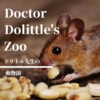

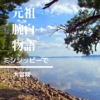


最近のコメント