【チョコレートがおいしいわけ】チョコレートってどこからくるの?バレンタインシーズンにおすすめの絵本。読み聞かせに。【4歳 5歳 6歳】
ぼくはカカ。わたしはポド。カカオ豆だよ。今日は、おいしいチョコレートがどうやってできるかを教えよう。チョコレートのもとは、はるか遠いアフリカ、ガーナにいるぼくたちカカオ豆のなかにあるんだ……
この本のイメージ チョコレートができるまで☆☆☆☆☆ 食育☆☆☆☆☆ わかりやすい☆☆☆☆☆
チョコレートがおいしいわけ はんだのどか アリス館
<はんだのどか>
1981年長崎県生まれ。東京家政大学卒業後、原田治主宰のパレットクラブ・絵本コースで絵本を模索、2005年にドイツに三ヶ月滞在、ベルギーのチョコレート博物館を訪れたことがきっかけとなり、チョコレートの絵本をつくることを思いつく。その後松田素子主宰の絵本ワークショップChabooksに参加、2008年から2009年にかけて各分野のチョコレート専門家に会い、カカオ産地のガーナ共和国を訪れるなどして、構想を練る。本書がはじめての絵本。

バレンタインシーズンなので、チョコレート関係の絵本をご紹介しています。初版は2010年。
現代社会で暮らしていると、食べ物はスーパーマーケットで完成品を買う生活です。
昔は、魚は魚屋さん、野菜は八百屋さん、肉は肉屋さん、豆腐は豆腐屋さんで買っていましたから、食べ物の完成品がどういうふうに出来上がるか、多少はわかったものでした。
コロッケやトンカツは肉屋さんで揚げていましたし、豆腐やがんもどきはお豆腐屋さんが作っていました。お店で焼いているパン屋さんがほとんどでした。
今は、コロッケもトンカツも、豆腐もお惣菜も、パンも、スーパーマーケットで袋に入って売っています。魚は切り身の状態でパックに入っています。
完成品しか知らない生活をしていると、自分の口に入るものがどこからどのようにやってきて、どんなふうにその形になったのか、考えないうちに口にするようになります。
けれど、よくよく考えてみたら、自分の口に入るまでには、たくさんの人々の仕事を介しています。
今年「スタジオジブリ」で映画化されると噂されている「君たちはどう生きるか」にも、主人公コペル君が自分の家にあるオーストラリアの牛乳から作った粉ミルク缶を見て、はるかオーストラリアからどんなふうに自分のもとへやってきたのか思いを馳せる場面があります。
食と経済がはるかな距離を越えてつながっていることを子どもが理屈ではなく感覚で気づく、印象深いシーンです。この絵本を読んでいて、あのシーンを思い出しました。
チョコレートも、遠い遠いアフリカのガーナから、様々な人々の仕事がつながって日本のわたしたちのもとへとやってきます。
この絵本では、甘くておいしいチョコレートが、ふるさとのアフリカ・ガーナでカカオ豆として生まれてからどんなふうに日本へやってくるのかが、わかりやすく、詳しく描かれています。
日本で子どもたちの手に渡るときにはきれいに成型されて美しい形やかわいい形になっているチョコレートですが、もとはすべて、はるかな遠い国のカカオ豆。それが何段階も複雑な工程を経て、あの形になって手元に届くのかと思うと、感慨深いですね。
絵本のラストでは、ガーナのチョコレート農園においしいチョコレートが届きます。
これは、わたしたちのために、心をこめてカカオを育ててくれている農園の人々への感謝と愛情の1ページです。

カカオ農園については、ちょっと内容が脱線してしまうので今日の記事内では多くは触れませんが、この本の取材協力に名前が書かれている不二製油さんは現在SDGsなどの取り組みとしてカカオのサステナブル調達を行っていますし、森永製菓さんもかつて「1チョコ for1スマイル」と言うフェアトレードチョコレートを販売していました。
「ふだん自分が口にしているものがどこから来ているのか」を、バレンタインやチョコレートをきっかけに考えられるようになるのは意味深いことです。
絵は可愛らしく、文章は読みやすく、ほとんどがひらがなで書かれていますが、たまに入る漢字にはすべて振り仮名が振ってありますので、50音が読めればコツコツとひとりで読むことが出来ます。
でも、文章がリズミカルで擬音もかわいいので、読み聞かせに。
内容をすべて理解することは出来なくても、きっと深く心に残ることでしょう。
この季節の読み聞かせに、ぜひどうぞ!
繊細な方へ(HSPのためのブックガイド)
ネガティブな要素はありません。
チョコレートが大好きなお子さまなら、きっと楽しいと思います。
ふだんの生活で、チョコレートをただ食べているだけでは知ることのない、詳しいつくり方が描かれています。関わる人たちがそれぞれ、おいしいチョコレートを作るために一生懸命働いています。
読後はもちろん、チョコレートかココアでひと休み。










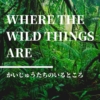
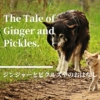
最近のコメント