【わたしはいいこ?】「いいこ」ってなあに?はじめて芽生えた疑問。子どもの自己肯定感を高める愛情たっぷりの絵本【4歳 5歳 6歳】
「いいこにしててね」。ママやパパは言うけれど、「いいこ」ってなんだろう?おともだちは言わないけれど、おとなが使うひみつのことば……わたしは「いいこ」なのかな?
この本のイメージ 自己肯定感☆☆☆☆☆ 愛情☆☆☆☆☆ はじめての哲学☆☆☆☆☆
わたしはいいこ? えがしらみちこ/作 小学館
<えがしらみちこ>
1978年福岡県生まれ。絵本作家、イラストレーター、絵本専門店「えほんやさん」代表(静岡県三島市)。主な絵本に『なきごえバス』(白泉社、「MOE絵本屋さん大賞2016」パパママ賞第1位)など。子どもが見せる一瞬の表情を水彩画でみずみずしく切り取る画風に、ファンが多い。

このブログでは定期的に、子どもの自己肯定感を高める絵本をご紹介しています。
「自己肯定感」とは、自己愛や自己中心的性格、自己正当化などの狭く閉じた感覚とはちがい、自分自身を欠点も含めて丸ごと受け入れる感覚のことです。
自己肯定感がもとから高い人は、むやみに自分と他人を比べて自分のほうが優れていると証明しようとはしません。そんなことをしなくても、もとから自分で自分を肯定しているからです。
一度や二度の失敗で自分が無価値になるとも思っていないので、自分の失敗を素直に認めることができ、他人の成功を素直に賞賛します。
自己肯定感が高い人間は、人生に余計な「圧」がかかっていないので自然体なのです。
逆に自己肯定感が低い人は、自分の低い自己肯定感を上げるためにあれこれと無理をします。これをバネに大成功する人もいるので、自己肯定感が低いことが必ずしもマイナスではないのではないか、とも言われます。
たしかに、低い自己肯定感を努力で補う人の頑張りはすばらしいものがあるのですが、往々にして生きづらさを感じ、追い詰められやすい部分があるのも事実です。
「自己肯定感」の高さは、人が長い長い人生を生き抜いてゆくとき、大きな困難や挫折を乗り越えてゆく助けになります。高い自己肯定感は、くじけない心の源となるのです。
では、その自己肯定感はどこから来るのでしょうか。
それは、地力では何も出来ない赤ちゃんの頃、そして、失敗ばかりの幼児の頃に、迷惑や失敗、至らなさのすべてをひっくるめて受け入れられた経験が育みます。
赤ちゃんは自力で食事をすることも出来ません。親にかけるのは迷惑ばかりで役に立つようなことはありません。歩き始めたばかりの幼児も同じです。親の役に立とうと何かをしようとしても、たいていは失敗して迷惑をかけてしまいます。
そんなとき、「それでもあなたは存在してくれるだけでうれしい」と言う、親の愛情を注がれて育つことが、自己肯定感をはぐくみます。
と、言葉で言うのは簡単ですが、難しい部分も多々あるのも事実。
まずは、この厳しい現代では親が忙しく様々な理由で心に余裕が無いこと、家事育児の負担が大きく、いつも愛情深く余裕をもっていることは難しいこと、なんでもないときに「生まれてきてくれてうれしい」「あなたが大好きよ」などと言う風習が日本人にはあまりないこと、などが理由として挙げられます。
よく「欠点や失敗を含めて子どもを肯定する」ことを「間違ったことをしても𠮟らない」ことだと誤解する方がいらっしゃるのですが、言うまでも無く子どもをしかることは(怒って激しい感情をぶつけるのではなく)大切なことです。
しかし、「そんな悪い子はうちの子じゃありません」とか、「わたしの子ならそんなことはしない」「あなたはもっといい子だと思っていたのに」と言うような、足場を失うような𠮟られ方をすると、「失敗すると子どもとして認めてもらえなくなる」と感じて自己肯定感を失ってしまうのです。
とはいえ、ここは本当に難しいところ……。
親にも親心があるし、子どもにも子どもなりの思いがあります。
そんな微妙な問題を、あたたかい絵本にしてくれたのがこれ。えがしらみちこ先生の「わたしはいいこ?」です。
おもちゃを散らかして遊んでいたとき、ママは「いいこなら ごはんのまえに おかたづけできるよね?」と言います。
パパは海で「うきわがふくらむまで いいこでまっててね」と言います。
「いいこ」ってなんだろう?
お友だちは言わないけど、大人は言う、「いいこ」って言うひみつのことば。
いいこって……
みんなのおせわをする、げんきであいさつ、かけっこはいつもいっとうしょう、パパのかばんをもってあげる、なきたくてもがまんする、たべおわったらおさらをはこぶ、お友だちがおもちゃを「かして」っていってきたらかしてあげる……
「いいこ」っていっぱいありすぎてつかれちゃう。
つかれちゃったのでママにきいてみました。
「ママ、わたしっていいこ?」
ママは優しく抱きしめてくれて……
……と、言うのがあらすじ。
この悩み、大人になってぶつかることもありますよね。実際「いい子」になろうとすると、その努力には果てがありません。欠点なんて探そうと思えば無限に見つかるからです。
かなり哲学的で大人っぽい悩みですが、子どもはそんなにばかでもないのでこれくらいの年齢で悩んでもおかしくはありません。ここまで言語化されていなくても、こんなようなことで悩んでしまうものです。
しかし、ここで「いいこでも いいこじゃなくても そのままのあなたが大好き」と答えるママの愛の偉大さ。
子どもが親に対して感じる複雑な想いと、それを受け止める母親の深い愛を、この短いページ数で一気に描ききっていて見事です。
また、そのような愛に包まれて育った子は、その後社会に出て「いいこ」を求められても精神的に潰れる事はない、と言うところまで描かれていて、そこもぬかりがなく素晴らしい。
なにより素晴らしいのは、これを「わが子に読ませてあげたい」と思う親心ではないでしょうか。
小さな子どもは自力で絵本を選ぶわけではないので、親からこの本をもらった子どもは幸せ者です。小さな心が不安でいっぱいのとき、お母さんお父さんからこの本を読んでもらえたら、どんなに安心するでしょう。
この本を選び、読ませたい、読んであげたいと思う方の愛情は、どんな困難からも立ち上がれる強い心を育めるはず。
この主人公は女の子ですが、この「いいこでいたい」「でもしんどい」と言う悩みは、幼い子どものころから大人になるまで「女の子あるある」なので、そこもリアル。
下の子が生まれたばかりの、頑張り屋の長女さんがいるおうちにおすすめです。本当は読み聞かせしてあげてほしいけれど、お忙しいならプレゼントするだけでも。
また、頑張っている人への差し入れやお見舞いなど、大人の和み本としてもおすすめ。遠くで働いている娘さんへ、救援物資の小包に忍ばせてみるのもいいかもしれません。
誕生日とか、クリスマスとか、そんな日ではなく、「なんでもない」「ふつうの日」のプレゼントに選んでいただきたい素敵な絵本です。
繊細な方へ(HSPのためのブックガイド)
ネガティブな要素はありません。愛らしい絵でつづられる、ちっちゃな女の子のけなげな気持ちと、それを受け止めるお母さんの深い愛の物語です。HSPの方、HSCのお子さまには特におすすめします。
自分で買うのもいいけれど、これはプレゼントで威力を発揮する絵本です。
小さな子なら読み聞かせに。子どもから大人まで、頑張る娘への差し入れやプレゼントにぜひどうぞ。





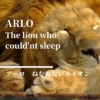



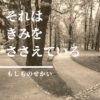
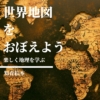
最近のコメント