【グレース・ホッパー】プログラミングってなあに? アメージングなプログラミングの女王の絵本。【4歳 5歳 6歳】
プログラムをしらべる じょうだんばかりいってる まがったことがきらい 話しじょうず トラブルをみつけるのがとくい 教えるのが好き 新しいことを考え出す 本を読むのが好き 海軍でリーダーになった きまりをきにしない チャンスにつよい でもときどきこまりもの アメージンググレース!(本書より)
この本のイメージ コンピューター黎明期☆☆☆☆☆ プログラミングとは☆☆☆☆☆ かっこいい女性☆☆☆☆☆
グレース・ホッパー プログラミングの女王 ローリー・ウォールマーク/文 ケイティ・ウー/絵 長友恵子/訳 岩崎書店
<ローリー・ウォールマーク>
科学の分野で活躍している女性たちを若い世代に伝える活動に熱心に取り組んでいる。プリンストン大学で生化学、ゴダード・カレッジで情報システム、バーモント・カレッジ・オブ・ファイン・アーツで児童およびヤングアダルト向け文学の学位を取得。最初に手がけた世界初のコンピューター・プログラマーの伝記絵本『Ada Byron Lovelace and the Thinking Machine』で数々の賞を受賞。ニュージャージー州リンゴーズ在住。
<ケイティ・ウー>
カリフォルニアのパサデナにあるアートセンター・カレッジ・オブ・デザインで、イラストとエンターテインメント・アートの美術学士を取得。グーグルやピクサーなどでイラストを手がける。ニューヨーク在住
<長友恵子>
翻訳家。訳書に『中世の城日誌』(岩波書店・産経児童出版文化賞JR賞受賞)などがある。紙芝居文化の会会員。やまねこ翻訳クラブ会員
※書籍に掲載されている紹介情報
小学校の授業にコンピュータープログラミングが採用される時代になりました。
本日は、プログラミングの歴史について語られている絵本のご紹介。コンピューターのプログラミングの歴史は、実は女性が深く関っています。
世界で一番最初のプログラマーと言われたのは、イギリスの女性、エイダ・ラブレス。
そして、コンピューターのプログラムを、人間にわかりやすい言葉にしたのが、このグレース・ホッパーです。
他にも、アポロ計画に深く関ったマーガレット・ハミルトンなど、歴史的なプログラマーには女性が多いのはなぜでしょうか?
それもそのはず、コンピューターが発明される以前のその昔、アメリカではペンと紙で複雑な計算をする人たちのことを「コンピューター」(計算手)と呼んでいた時代があり、最盛期で大活躍したのは、女性たちだったからなのです。
そのような歴史があり、アメリカでは女性が頭脳労働をすることに抵抗のない土壌が生まれたのでしょう。素敵なことですね。
さて、今回も知人のプログラマーに少しだけ推薦文をかいていただきました。それでは、どうぞ!
「グレース・ホッパー」
プログラミングの女王という副題にあるとおり、デジタルコンピュータの黎明期に活躍した数学・プログラミングの天才。
プログラム言語COBOLの開発者であり、0と1の数字しか扱えなかったコンピュータに英語を教えた初めての女性。アメイジング・グレイスと呼ばれたグレース・ホッパーの生涯をやさしく紹介した絵本です。 最初に紹介されるのはコンピュータプログラミングでよく出会う「繰り返しの無駄」についてのエピソード。
同じ計算や処理をコンピュータにさせるのなら、同じコードを何度も書くのは無駄でしかありません。そんなことは一度のコーディングですませてしまおう。という、今となってはごく当たり前の考え方。
それを、彼女は最初に実用化し、徹底しました。今と違ってメモリも処理速度も貧弱だった当時のコンピュータでは、こうした考えの恩賜は計り知れない物でした。
※海軍で彼女が最初に扱ったコンピュータは「Harvard Mark I」という超巨大コンピュータで、アメリカ初の電気機械式計算機とされています。 総重量はなんと4.5トン。一秒間に3回の加算または減算ができるというハイスペック! 乗算には6秒かかり、除算は15.3秒、対数や三角関数の計算には1分以上かかったそうです。
そして、有名なのがこの「Harvard Mark I」のハードウェアの中に紛れ込んでいた「虫」がコンピュータを誤動作させた、(そしてその虫を発見した)というエピソード。
そのバグ(虫)を取り出して(デバッグ)した彼女は、「本物のバグ(虫)がコンピュータのバグとして発見された初めての例」として、記念にその虫を自分の日記に張り付けたそうです。(この日記は今もスミソニアン博物館に保存されています)
この本は、そうした数々のエピソードと、その時々に残した彼女の名言がいくつも紹介されています。子供だけでなく、デジタルコンピュータの歴史に興味のある方すべてにお勧めです。
アメリカでは、最近、こういう絵本や児童書が精力的に出版されています。なぜなら、優秀なプログラマーを育てるためには、まずあこがれてもらうところからはじまるから。
だから、かっこいい女性、活躍した女性の伝記がこのように絵本になっているのです。
日本のテレビドラマでは、IT関係者やコンピュータープログラマーと言うと、金の亡者か犯罪者かみたいな設定が多くて、密かにがっくりしてしまいます。でも、こんな素敵な絵本があれば、プログラミングに興味を持ってもらえるかも。
プログラムって何? どんなことするの? 小さなお子様が興味をもてるような、かっこよくて素敵な絵本です。
プログラミングに限らず、考えること、学ぶこと、問題をみつけて解決することは、面白くて楽しいものです。道を切り開いた人たちは、みな、新しいものが好きで、好奇心にあふれ、凝り固まった考えを突破してゆく人たち。
どんな人もそれぞれ、その人だけの「何か」があるはずです。
逆まわりの時計を見て、ドラゴンや妖精の絵を描いて、「ありそうにないもの」を頭に描きながら、問題を解決していったグレース。彼女は、80歳で海軍をやめるまで、「考える」ことで働き続けました。
考えをめぐらせることや、頭を使うこと、そういうことを女がすると「小ざかしい」「ずるがしこい」「かわいげがない」などと言われがちな時代(日本では今でも言われます)に、なんという功績でしょう。
がんばる女の子の背中を押し、学ぶことや考えることの楽しさを伝えてくれる、かっこいい絵本です。
繊細な方へ(HSPのためのブックガイド)
ネガティブな要素はありません。女性が「考えること」を仕事にしてもいいんだ、と言う、励まされる伝記です。
コンピュータープログラミングの歴史においてグレース・ホッパーが成し遂げたことがわかりやすく書いてあります。幼いグレースからおばあちゃんになったグレースまで、瞳がキラキラと輝いて、好奇心いっぱいの表情がとても幸せそう。
学校での授業を受ける前に、コンピュータープログラミングについて興味を持ってもらうために、最適です。
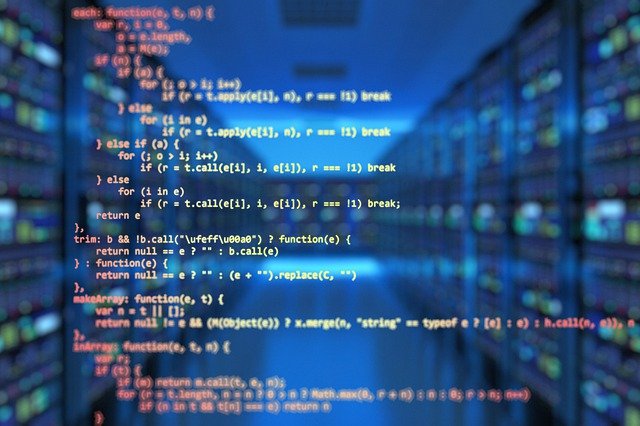

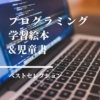



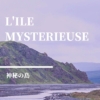

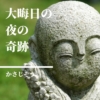
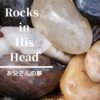



最近のコメント