【カスピアン王子のつのぶえ】角笛に呼ばれてナルニアへ!ファンタジーの名作ふたたび【ナルニア国ものがたり】【小学校中学年以上】
ピーター、スーザン、エドマンド、ルーシィのペベンシーきょうだいは、駅で学校に戻る電車を待っている途中に魔法の力でナルニアに呼ばれます。そこでは、前の時代から数百年の時が流れていて……
この本のイメージ わくわく☆☆☆☆☆ 不思議☆☆☆☆☆ 冒険☆☆☆☆☆
カスピアン王子のつのぶえ ナルニア国ものがたり 2 C・S・ルイス/作 瀬田貞二/訳 岩波少年文庫
<C・S・ルイス>
本名クライブ・ステープルス・ルイス(Clive Staples Lewis 1898年11月29日 ~ 1963年11月22日)。アイルランド系のイギリスの学者、小説家、中世文化研究者、キリスト教擁護者、信徒伝道者。全7巻からなるハイファンタジー小説『ナルニア国物語』の著者として有名。

世界三大ファンタジーのひとつ、ナルニア国ものがたり第2巻のご紹介です。(ちなみに、残りのふたつは「指輪物語」と「ゲド戦記」です)原題はPrince Caspian: The Return to Narnia.初版は1951年。日本での初版は1966年です。
この本の冒頭で、ナルニアの歴史が少し語られていますが、このお話は、「ライオンと魔女」の続編にあたります。ナルニア国ものがたりは、どの巻から読んでも楽しく読めるようになっていますが、大きな歴史の流れがあり、第1巻と第2巻はその中盤のお話。
主人公もかなり入れ代わりがありますが、ルーシィ・ペベンシーは重要人物として、多くのお話に関ります。
今回のストーリーは……

夏休暇を終え、駅で電車を待っていたピーター、スーザン、エドマンド、ルーシィのペベンシーきょうだいは、突然、強力な魔法の力でナルニアに呼び込まれました。
しかし、それは、以前彼らが王と女王として治めていたナルニアから数百年経っていたのです。
そのころのナルニアはテルマール人が治めていました。ナルニアの王子カスピアンは、叔父のカスピアン王ミラースに育てられましたが、もの言う動物や妖精たちと共存していた大昔のナルニアに憧れていました。
さて、ある日、ミラースに息子が生まれます。息子が生まれたからにはカスピアンは不要になるだろう、と家庭教師のコルネリウスに忠告され、カスピアンは暗殺を逃れて城を脱走します。
ミラースの軍に追われたカスピアンは、かつてスーザンがクリスマスプレゼントとしてもらい、ナルニアに置いていった「吹けば必ず助けが来る角笛」を吹きました。
どうやら、ルーシィたちは、その角笛に呼ばれたらしいのです。
さて、ルーシィたちは無事カスピアンに合流することができるのでしょうか。そして、ナルニアの運命は?
……と、いうのがあらすじ。
「ナルニア国ものがたり」は、作者のC・S・ルイスが敬虔なキリスト教徒であり、キリスト教の教えを子どもたちにわかりやすく教えるために書かれたファンタジーだといわれています。
そのため、1巻の「ライオンと魔女」でも、きょうだいのなかで一人裏切り者がいたり、そのためにライオンの救世主アスランが石舞台で殺され、その後復活したりと、聖書にまつわるエピソードが入っています。
この「カスピアン王子のつのぶえ」も、アスランが見えるルーシィと見えないピーターたちのやり取りなどに、宗教的な比喩が感じられます。が、そのようなことを読み取れなくても、不思議で、わくわくした冒険物語として楽しめます。
ファンタジーが好き、と言うと、よく言われるのが「現実逃避」と言う言葉。
SFが好き、ファンタジーが好き、アニメが好き、漫画が好き、と言うと、社会性がないとか現実と向き合っていない、とかよく言われますよね。
なので、保護者の方のなかでも、お子さまにファンタジーやSFは読ませない教育方針の方も多いはず。けれど、ファンタジーやSFは、子どもの情緒を育て、想像力を羽ばたかせる効果があります。また、推理小説は、論理的に考える力を与えます。
それに、世の中が豊かで平和だった昭和後期や平成前期と違って、今は天変地異も多く、不景気で、しかも伝染病など、たいへんなことばかり。現実のあれこればかりを考えていたら、耐えられなくなることもあるでしょう。こんな過酷な時代に生きている子どもたちには、夢や空想が必要です。
特に、風雪を耐えた名作児童文学や、古典ファンタジーには、情操教育的要素があります。
傷つきやすい子どもの心に寄り添い、前向きで明るい考えへと導いてくれる名作が多く、大人になってから読んでも癒されます。
ナルニア国ものがたりの魅力は、ほかにもあります。
女の子が強いのです。
主人公はルーシィ。ペベンシーきょうだいの末っ子です。ナルニアの一の王であり、長男なのはピーターで、いざというときに戦うのもピーターなのですが、いつも大事なことに気がつき、正しい方向にみんなをみちびくのはルーシィなのです。
そして、ルーシィも、姉のスーザンも、いざと言うときは戦います。
スーザンは、百発百中の弓の名手。今回も、弓で小人のトランプキンを助けます。
女の子が強いファンタジーは、さわやかな魅力があります。
昔のおとぎ話では、女の子が強いことはあまりなくて、強くなると魔女とか悪役になってしまうことが多いかったのです。男の子の場合は強い=正義なのに、女が強くなるとどうして悪なのか……。小さい頃はちょっぴり不満でした。
いまは、日曜日の朝など、強い女の子の正義の味方もたくさんいるし、いい時代になりました。
女の子の生き方にだんだんと選択肢が増えてきているのだと思います。もちろん、まだまだたくさんの固定観念があるんですが、そのような縛りを最初にはずしてくれるのがファンタジーなのです。
ファンタジーやSF、ミステリの世界では、現実にはおこりえないことがおこりますから、現実の世界よりさまざまなことが一歩も二歩も進んでいます。
たとえば、児童向けミステリ「ナンシー・ドルー」を読んで育った女性たちが、今、アメリカで活躍しているように、児童文学や漫画、アニメーションに影響を受けた子どもたちは、未来を変えてゆく力を持つことが出来ます。
そして、かつてファンタジーだったものは、科学の発達により、現実になります。
こんなことを考えていると、本当に胸が熱いですね。
自動車が発明されたのは1769年。
普及しはじめたのは、1865年です。
エジソンが電球を発明したのは、1879年。
ライト兄弟が初飛行したのが1903年。
150年前には電灯も飛行機もなかったのです。そして、この頃の児童文学を読んでいると、急速に馬車が自動車になり、ランプやろうそくが電灯になってゆくのがわかります。
とくに、ビフォーエジソンとアフターエジソンでは、別世界です。
このような時代に生み出された児童文学は、人間の可能性への希望に満ちており、生命力にあふれています。しおれかけた現代人の心に栄養を与えてくれ、どっしりと根の生えた感情を呼び起こしてくれるのです。
また、「ナルニア国ものがたり」に代表される、第2次世界大戦直後に生まれたファンタジーには、子どもの幸せな人生への祈りが込められており、あたたかな父性や母性に満ちています。この時代は、良質のファンタジーが数多く生まれた時代でもあり、夢をみること、空想することが生きる力になることを教えてくれます。
ファンタジー、と言うだけで「現実を見ていない」とか「自分の世界に閉じこもっている」と言われがちですが、もし、まだであれば、一度、児童文学の古典を読んでみてください。おどろくほど骨太の話ばかりだとわかります。
三大ファンタジーのなかでも「ナルニア国ものがたり」はお子さまに理解しやすく、わかりやすい物語です。
小さな子どもが好奇心いっぱいの冒険を楽しむのもよし、大人が読んで、かつてのなつかしい子供心に会いに行くのもよし。
外出できないお休みこそ、良質のファンタジーをお楽しみください。
繊細な方へ(HSPのためのブックガイド)
最初に申し上げて起きますと、「ナルニア国ものがたり」シリーズの最終巻「さいごの戦い」は、HSPやHSCにとっては、ちょっとショックな展開が待っています。
この「カスピアン王子のつのぶえ」だけでしたら、とても明るく、良い話だと思います。シリーズを最後まで読んだとき、ちょっぴり切ない気持ちになるかもしれませんが、「そういう話なのだな」と身構えていたら大丈夫な方ならおすすめです。HSPやHSCのほうが、深く、たくさんのメッセージを受け取れると思います。
古きよき時代のファンタジーです。ナルニアファンに愛される、ねずみの騎士、リーピチープが初登場します。
読後は、りんごやぶどうが食べたくなるかもしれません。


![ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51dWGFH0NIL._SL500_.jpg)
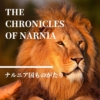


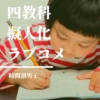




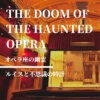
最近のコメント