【ねずみ女房】鳩とねずみの友情と、それが残したもの。大人にもおすすめの絵本【読み聞かせ】
バーバラ・ウィルキンソンさんの家に、とあるねずみ夫婦が巣を作っていました。ある日、ウィルキンソンさんがきじばとを鳥かごにいれて飼いはじめます。ひょんなことから、めすねずみは、このきじばと友達になりました。けれど、きじばとは、日に日に弱っていったのです……
この本のイメージ 動物の友情☆☆☆☆☆ 夢とは☆☆☆☆☆ 哲学☆☆☆☆☆
ねずみ女房 ルーマ・ゴッデン/作 W.P.デュボア/画 石井桃子/訳 福音館書店
<ルーマ・ゴッデン>
マーガレット・ルーマー・ゴッデン(Margaret Rumer Godden, OBE, 1907年12月10日 – 1998年11月8日 )イギリスの作家。
1907年イギリスサセックス州生まれ。生後まもなく家族と共にインドに移り住み、12歳の時にイギリスに戻る。「人形の家」「ねずみ女房」「ハロウィーンの魔法」など。

絵本の中では古典の部類に入ります。子供向けの絵本ではありますが、親子で読んでいただきたい絵本です。「クマのプーさん」や「ちいさいおうち」で有名な、石井桃子翻訳です。
原題はThe Mousewife. 原書初版は1951年。日本語版初版は1977年です。
あらすじは単純で、
とあるねずみの夫婦が、ウィルキンソンさんの家に巣を作っています。ごくふつうのおすねずみと、ごくふつうのめすねずみでしたが、めすねずみは実は、ちょっとふつうとは変わっていました。
毎日の生活に、「このままでいいのかな」と思い始めていたのです。
そんなとき、1羽のきじばとがウィルキンソンさんの家で飼われることになります。
鳥かごの中には、上等の豆があるので、めすねずみはそれを狙って鳥かごの中に入ります。ところがはとは与えられた餌を食べようとはせず、日に日に弱っていきました。
めすねずみは、はとの豆をもらうかわりに、はとの食べられそうなパンくずを運んでやります。そのうちに友達になります。
はとは、めすねずみに空を飛んだ時の気持ちや、山の上からの風景や、外の世界の話をします。はとは帰りたいのです。
やがて、めすねずみは、はとを逃がしてやります。はとは自分のいるべきところへ戻ってゆきました。
と、いうお話です。
これは「教訓」的童話ではなく、感受性の童話です。ですから、本日のレビューは多分にネタバレを含んでしまいます。本当に申し訳ありません。
※もし、あらすじを読んでこの絵本を買ってみよう、と思われた方は、レビューを読むのはここまでにしてください。「もう少し読んでみてから、買うかどうか決める」と言う方は、この先へお進みください。
教訓的なお話と言うのは、主人公なり、キャラクターが何か至らないことや悪いことをして、それにより不幸になり、反省して善く生きようとするようなお話です。教訓だと思うと、「はとが飛び去ってしまったときにどうしてお礼を言わないんだろう」、とか「どうしてはとは恩返しをしないんだ」、とか「どうしてねずみ女房の生活は、はとを助けたあとも変わらないんだろう」とか、いろいろと疑問が出てきます。
もちろん、この絵本の中に個人が教訓を見出す事はできます。困っている人は助けよう、とか狭い世界に閉じこもるのはやめよう、とか。けれども、もしそれがテーマならば、はとの恩返しがあるはずだし、ねずみは家を捨てて出てゆくはずです。
この童話は、感受性を持たない人たちのなかで生きる感受性の高い人の人生について、あざやかに描いています。おそらく、作者は自分のことを描いたのでしょう。
狭い巣の中で生きるめすねずみは、広い野原も高い空も、山も海も知りません。知っているのは薄暗い床下と天井裏、そして、ウィルキンソンさんの家だけです。そこに、外の世界からはとがやってきます。
めすねずみははとと仲良くなり、はとから見た世界を教えてもらいます。
はとと仲良くなれる時点で、このねずみはそもそもふつうのねずみではなかったのです。はとの言葉を理解し、はとの世界を聞いて、それを想像したり考えたりすることができるめすねずみは、その段階で、「自分ではない人の視点で考えることができる」ようになっています。めすねずみの視点は大きく広がっているのです。
めすねずみは、日に日に弱っていくはとに母性を抱き、そして、「このはとは、ここのままこの家にいてはいけない」と考えます。この時点で、めすねずみは、自分で考えて自分で判断を下しています。
そして、ある夜、ウィルキンソンさんの家の窓が開いているのに気づき、めすねずみは、はとをかごから出して逃がしてやるのです。
はとと別れて、めすねずみの生活は、もとの生活に戻りました。
でも、めすねずみは、ふつうのねずみとはどこかちがったので、みんなはめすねずみを大切にしました。
ごくふつうのめすねずみは、どうして「どこかちがう」ねずみになったのでしょうか。
めすねずみの生活は、その後もふつうのねずみの生活のまま、何も変わりませんでしたが、目に見えないものを得たので、ひいまごたちは、このおばあちゃんねずみをとても敬いました。
この「見えない何か」が、「赤毛のアン」で大人になったアン・シャーリーが周囲の人たちに「言葉で表現できない魅力がある」と言われるところであり、「クローディアの秘密」で「秘密」と言われているものであると、わたしは思います。
この物語の感想は別れると思います。最初と最後でめすねずみの状態はまったく変わらないので「何を言っているのかわからない」と感じる方がいる一方、深いメッセージを受け取り、涙を流す方がいるでしょう。
この童話が出版されて、いまでも販売され続け、21世紀のわたしたちが読むことができるのは僥倖だと感じます。
なぜなら、この童話が出版社を通過するときに「わけがわからない」と却下されたり、はとが恩返しをするように、またはねずみが狭い世界を捨てて自立への旅に出るように、ラストの書き換えを要求されることもありえたからです。むしろ、現代のほうがそうなる可能性が高い。
そのほうが、子どもにとって、あきらかにわかりやすい物語ですから。
作者は童話は母親が子どもに読み聞かせるもの、かならず母親は子どもと一緒に読んでくれるはず、と願いを込めてこれを書いたのでしょう。それに、当時の「絵本を読む子ども」は上流階級でしたので、学校には行かず自宅という狭い空間で乳母や家庭教師に育てられていましたから、感受性の強い子どもなら、このお話からめすねずみの気持ちは感じ取れると、期待したはず。
このおはなしが、このまま出版され、そして、現代のわたしたちの手元にとどくこと、この本を翻訳してくれた石井桃子先生に、深い感謝の念を抱きます。
令和の今、インターネットにつなげればたくさんの情報が入ってきます。もちろん、実際に見て体験することが最上です。けれども、あらゆることに対して実際に現地に行って、自分の力で世界中のすべてを見ることは、それが最上だとわかっていても、さすがにできません。
そして、コロナ禍の今は、以前に比べると、外出自体が非常に難しくなりました。
「知る」ことは無意味でしょうか。
そして、何かを知ったとき、それを知らない人と争ったり戦ったり、上下を決めたりする必要があるでしょうか。外の世界の多くのことを知ったあとも、めすねずみはおすねずみと喧嘩したり、ほかのねずみたちを馬鹿にしたりすることなく、仲良く暮らしおばあちゃんねずみになります。
「知る」ことは、他人との関係でどうこうするものではなく、純粋に自分自身のためだけに輝くからです。
人間というものは案外自分の狭い世界からはなかなか出ることができないし、それが一概に悪いとも言えないと思います。女性だけでなく、子供も働く男性も、教室や職場の部署などの狭いコミュニティと自宅の往復で、そんなに簡単に「広い世界」に飛び出してゆくことはできません。
けれど、どこにいても、移動できなくても「知る」ことはできます。このねずみは、少しだけ踏み出し、自分の力で星を見ることができました。知らない世界を知ることができたのです。
受け取れる人だけが、しみじみとした感慨を感じることができる童話です。わかりやすいお話ではありませんが、わたしは名作だと思います。
お子様が自分で読むなら小学校低学年以上でしょうが、読み聞かせを前提に書かれている絵本なので、どうぞお子様が小さいときに、一緒に読んであげてください。
繊細な方へ(HSPのためのブックガイド)
ネガティブな要素はありません。HSCの方や、HSPの方のためのような絵本です。読み聞かせにおすすめです。感受性の高い方なら子どもでも大人でも、多くのことを受け取けると思います。今、職場やご家庭でがんばっている女性には、ぜひ読んでいただきたい絵本です。しみじみと励まされます。



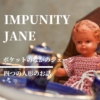


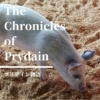


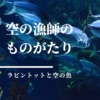


最近のコメント