人はどうして争うの?平和な世界ってどうしたら作れるの?小さな子どもがはじめて出会う疑問に、絵本が寄り添います。すぐに答えが出る問題ではないけれど、「考える」ことをはじめよう…… 平和について考える絵本を当サイトの独断と偏見で10冊、選びます。
ペイフォワードの心を表現した、やさしい世界の絵本。うさぎさんが、小さな木の椅子を作ります。「どうぞの いす」と書いた立て札を、隣に立てて。 そこへどんぐりのかごを持ったろばさんがやってきます。
どうぞのいすにどんぐりを置いて、ろばさんはうとうと眠り始めました。

人は、それぞれみんな一人に一つ、「見えないバケツ」を持っている。そのバケツは、良い心や良い気持ちになるといっぱいになり、バケツがからっぽになると哀しい気持ちになる。
バケツをいっぱいにする方法は、他人のバケツをいっぱいにすること。誰かに微笑みかけたり親切にしたり、好きな気持ちを伝えたりすると、バケツはいっぱいになる。
誰かのバケツをからっぽにしたら自分のバケツがいっぱいになると信じている人がいるけど、それはまちがい。
他人のバケツをからっぽにする人のバケツはたいていからっぽ……
人間関係のトラブルの本質を教えてくれ、幸せで平和な世界へのヒントを与えてくれる絵本です。4歳から。
※「しあわせのバケツ」のレビューはこちら↓
平和について考える絵本 おすすめ第6位 はなのすきなうし 岩波の子どもの本 マンロー・リーフ/おはなし ロバート・ローソン/絵 光吉夏弥/訳 岩波書店

実在した牛をモデルにした有名なメルヘンです。アメリカではアニメーション映画化されています。
フェルジナンドは、争いや戦いが大嫌いな、おだやかで優しい牛でした。
ほかの牛は角を自慢しあって、争いあい、いつか闘牛になることを夢見ていますが、フェルジナンドは闘牛なんてとんでもない。
ひとりでコルクの木の下で、花の匂いをかいでいるのが好きなのです。
ところがあるとき、くまんばちに刺されたフェルジナンドは、あまりの痛さに大暴れ。
荒々しい牛と勘違いされ、牛買いたちにマドリードの闘牛場に連れ去られてしまいます……
ナチスドイツ時代、ヒトラーによって発売禁止処分になっていたと言う伝説の絵本。おだやかで優しい、でもわが道をゆくフェルジナンドの物語を読めば、平和へのヒントが見つかるかもしれません。4歳から。
※「はなのすきなうし」のレビューはこちら↓
平和について考える絵本 おすすめ第5位 せんそうがやってきた日 ニコラ・デイビス/作 レベッカ・コッブ/絵 長友恵子/訳 鈴木出版

ある平和で平凡な日、突然「戦争」がやってきた……。
恐怖のなか、逃げて逃げて、自分の居場所を探す少女の物語。
戦火から逃げてくる小さな女の子の様子が詳細に描かれています。自分を取り巻く幸せな世界が突然崩壊するショック、一人ぼっちで逃げるつらさ、苦しみ、みじめさ、そして、暖かい場所へとたどりつく安心感などが、小さな読者にもわかるよう、丁寧に描かれています。
絶望的な状態から始まるお話ですが、希望に満ちた形で締めくくられています。 4歳から。
※「せんそうがやってきた日」のレビューはこちら↓
平和について考える絵本 おすすめ第4位 子どもの本で平和をつくる イェラ・レップマンの目ざしたこと キャシー・スティンソン/文 マリー・ラフランス/絵 さくまゆみこ/訳 小学館

実在したユダヤ人女性、イェラ・レップマンの活動を小さな女の子の視点から描いた物語。
イェラ・レップマンはドイツ将校の妻としてドイツで暮らしていましたが、第一次世界大戦での夫の死後、編集者として働き、その後、ナチスドイツの台頭により、二人の子どもと共にイギリスに移住します。
そして、第二次世界大戦後はドイツにもどり、子どもたちに絵本を読ませる「絵本の展示会」を開催することで、ドイツ再建に力を尽くしました。彼女の展示した絵本の中には、ナチスドイツに禁止されていた絵本もあったそうです。
また、953年にチューリッヒで非営利の国際児童図書評議会(IBBY)を設立しました。設立メンバーには「長くつ下のピッピ」のアストリッド・リンドグレーンも参加しています。 5歳から。
「子どもの本で平和をつくる」のレビューはこちら↓
平和について考える絵本 おすすめ第3位 暴力は絶対だめ! アストリッド・リンドグレーン 石井登志子/訳 岩波書店

1978年、アストリッド・リンドグレーンがドイツ書店協会平和賞の授賞式で行ったスピーチを小さな本にまとめたもの。
ハードカバーの小さい、薄い本で、スピーチ部分は18ページ、あとは解説で成り立っています。
「平和な世界はどうしたら創れるのか」を、リンドグレーンなりに出したひとつの答です。
それが正しいかどうか、また、それが唯一なのかどうかは、わかりません。リンドグレーン自身もわからないけれど「試してみる価値はある」と言う提案でした。
平和な世界をつくるためにはどうすればいいのか、先人たちが悩み、考え、知恵を絞っていたことがわかる小さな本です。小学校中学年以上。
※「暴力は絶対だめ!」のレビューはこちら↓
平和について考える絵本 おすすめ第2位 なぜあらそうの? ニコライ・ポポフ/作 BL出版

この絵本には文章がありません。
しかし、絵だけで、人と人が争い、それが集団対集団の争いになり、どんどんエスカレートして最終的に誰も得をしない状態になってゆく様子が描かれています。
1996年にスイスで出版されてから、世界中で出版されているロングセラー絵本。
作者はロシアの方のようですが、ロシアでは今、この絵本は入手できるのでしょうか……?
今こそ、読みたい絵本です。文章がないので、どんな年齢の方にも。
※「なぜあらそうの?」のレビューはこちら↓
平和について考える絵本 おすすめ第1位 動物会議 エーリヒ・ケストナー/作 ヴァルター・トリアー/絵 池田香代子/訳 岩波書店

ナチスドイツ時代、著書が次々と発売禁止になったケストナー。そのケストナーが第二次世界大戦後に子どものためにつくった絵本です。ドイツでの初版は1949年。愛されるロングセラーです。
長く続いた戦争が終わったばかりだけれど、またはじまるかもしれず、先行きが不透明なまま、ふつうの人々は不安を抱えて暮らしていました。そんなとき、動物たちが平和な世界をもたらそうと、自分たちが率先して平和会議を行おうと決心します。
子どもたちのために。
さて、動物たちの行動は、平和をもたらすことができるのでしょうか?
絵本という形にはなっていますが、文章が多く、短編小説くらいのボリュームがあります。しかし、作者の想いが詰まった絵本なので、子どもから大人まで平和について考えたい人なら、おすすめです。
ケストナーの信念と祈りを感じる絵本です。小学校中学年以上。
※「動物会議」のレビューはこちら↓
世界には、一個人の力ではどうしようもない理不尽や不幸がたくさんあります。しかし、どんな人にも「考える」ことはできます。本を読めばすべての答えがわかるわけではありませんが、本はいつも悩みや苦しみに寄り添ってくれます。
1日も早く、穏やかな日々がやってきますように。
お気に入り登録をしてくださればうれしいです。また遊びに来てくださいね。
応援してくださると励みになります。






















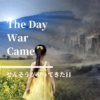








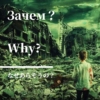










最近のコメント