【ユメミザクラの木の下で】日本のムーミン谷? 春に読みたい、ちょっとせつないファンタジー。こそあどの森の物語第4巻【こそあどの森の物語】【小学校中学年以上】
野原で不思議な女の子「ウサギ」に出会ったスキッパー。ウサギの友達たちと一緒にかくれんぼをして遊びます。ところが、途中で彼らを見失ってしまい、スキッパーは探し回るのですが、そこで彼は不思議な桜の木を見つけるのでした……
この本のイメージ かくれんぼ☆☆☆☆☆ お花見☆☆☆☆☆ ノスタルジー☆☆☆☆☆
ユメミザクラの木の下で こそあどの森の物語 岡田淳/作 理論社
<岡田淳>
日本の児童文学作家。著書『雨やどりはすべり台の下で』で産経児童出版文化賞を、『こそあどの森の物語』で野間児童文芸賞を受賞し国際アンデルセン賞の国際児童図書評議会(IBBY) オナーリストに選ばれた。翻訳家、挿絵・イラスト作家、エッセイストでもある。

この森でもなければ
その森でもない
あの森でもなければ
どの森でもない
こそあどの森
こそあどの森 (引用 表紙カバー折り返しより)
「日本のムーミン谷」とも呼ばれる、「こそあどの森」シリーズ、4巻目は「ユメミザクラの木の下で」。初版は1998年です。
「こそあどの森」シリーズは一話完結形式で、どの巻から読んでもわかるように書いてありますが、この世界観を理解するためには、まずは世界設定や住人たちを詳しく描いている第一巻を読んだほうがわかりやすいと思います。
第1巻のレビューはこちら。↓
さて、今回のお話は……
バーバさんから手紙が届きました。
そこには「かくれんぼをしているこどものようにわくわくしている」と書いてあり、バーバさんから「かくれんぼ」と言う遊びがあると教えられたことを思い出したスキッパー。
でも、スキッパーはバーバさんと二人暮らしで育てられ、こそあどの森にはほかに子供がふたごしかいないので、「かくれんぼ」をしたことがありません。
聞いた事はあるけれど、どんな遊びなのだろう?
そんなことを考えていたとき、「ウサギ広場」と名づけた野原で女の子に出会います。スキッパーは彼女を「ウサギ」と呼び、彼女はスキッパーを「ハリネズミ」と呼んで仲良くなります。
ウサギと一緒に遊び、彼女を追いかけていたら、ウサギの友達の男の子三人と女の子一人に出会い、ふたごたちも合流してみんなでかくれんぼをすることになりました。
スキッパーは生まれてはじめてかくれんぼをして遊びます。
ちょうどそのころ、こそあどの森の大人たち、ポットさん、トマトさん、トワイエさん、ギーコさん、スミレさんの五人は、満開の桜の大木の下でお花見をしていました……
……と、いうのがあらすじ。
昔の子供たちの定番の遊び、そのひとつがかくれんぼだと思います。
かくれんぼの歴史は古くて、発祥は確かではありませんが中国の唐の時代と言われています。このブログでもご紹介した「なかなおりの魔法 トゥートゥルと不思議なともだち」でも子どもたちがかくれんぼをするシーンがあります。リンドグレーンの「カッレくんの冒険」(新訳版では「名探偵カッレ 地主館の罠」)でも、かくれんぼのシーンがあり、世界中で遊ばれている遊びのようです。
日本では、良寛和尚が子どもたちとかくれんぼをする逸話が残っていますから、良寛和尚が宝暦8年10月2日(1758年11月2日)~天保2年1月6日(1831年2月18日)の人だとすると、江戸時代後期にはかくれんぼは非常にポピュラーな遊びだったとわかります。
デジタルゲームがなかった頃の遊びとしては、ほかには、男の子は缶蹴り、陣取り、女の子はゴムとび(不思議と男の子はゴムとびをしなかった)、「ケンケンパ」、「だるまさんがころんだ」、「チョコレート・パイナップル・グリコ」(これは名称に地域差があり)などがありました。
最近の子どもたちは、どの程度知ってるのでしょうかしら? 確かに、わたしもそれは知りたいところでした。岡田先生は、長年小学校の先生をされていたので、このあたりのことが肌感覚でご存知だったのだと思います。
不思議な女の子「ウサギ」に出会ったスキッパーは、女の子から「花冠」の作り方を教わります。(これも、最近はするのでしょうか。わたしの小さい頃はクローバーで花冠を作るのと、タンポポの綿毛飛ばしは定番の春の遊びでしたが……)
その後、ウサギの友達たち4人とふたごたちと合流してみんなでかくれんぼをして遊びます。
ここは、かなり詳しくて、かくれんぼを知らない子どもでも、読めば「こういうものか」とわかるようになっているのです。やさしい。
スキッパーは生まれてはじめて、たくさんの子どもたちと一緒にかくれんぼをして遊ぶのでした。
後半は、「ウサギ」の謎、そして、不思議な花「ユメミザクラ」のお話になります。
これねえ、このお話は、大人が読んだほうが心にしみるものがあると思います。
ノスタルジーをテーマにしたファンタジーには、時を超えるお話が一般的ですが、今回のお話ではタイムトラベルはしません。しかし、大人が忙しい生活の中で忘れていた幼心を思い出させてくれる仕掛けがあって、その斬新さにやられました。 こうきたか!
「こそあどの森」は、幻想と現実が交錯するお話が多く、夢と現実の境目があまりない子どもの頃の感覚と似ています。岡田先生はあの頃の感覚を忘れてないんですね。
字は大きく、そんなに漢字も多くないので小学校中学年から楽しく読めると思います。かしこい子なら低学年から読めると思います。かくれんぼする年齢は低学年なので、できればその年頃の子に呼んで欲しいかも。できれば、足りない振り仮名は保護者の方が追加してあげてください。
感受性がするどいお子さま向けです。
岡田先生は美大卒で美術の先生だったので、挿絵はご自分で描かれています。文章を書いているときに映像が浮かぶタイプらしく、美しい情景がありありと浮かんできます。
内向的で感受性がするどいお子さまに、おすすめの物語です。もちろん、大人が読んでも楽しめます。この本は、桜の季節にぴったり。
水筒にお気に入りのお茶をいれて、公園のベンチで読むのがおすすめです。
絶対、お花見したくなる物語です。
繊細な方へ(HSPのためのブックガイド)
ネガティブな要素はありません。ノスタルジックで繊細で美しいメルヘンファンタジーです。春にぴったり。
きついシーンがひとつもなく、全編ほのぼのとした、あたたかさに満ちた物語です。
内向的なお子さまに、また、物語が好きな大人の方にも、自宅療養のお見舞いやプレゼントにもおすすめです。
読後は、おいしいお茶と串団子を持って、公園でお花見しましょう。できれば桜を見たいものですが、花があるところならどんなところでも気持ちがいいと思います。






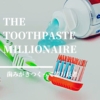

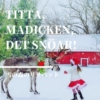


最近のコメント